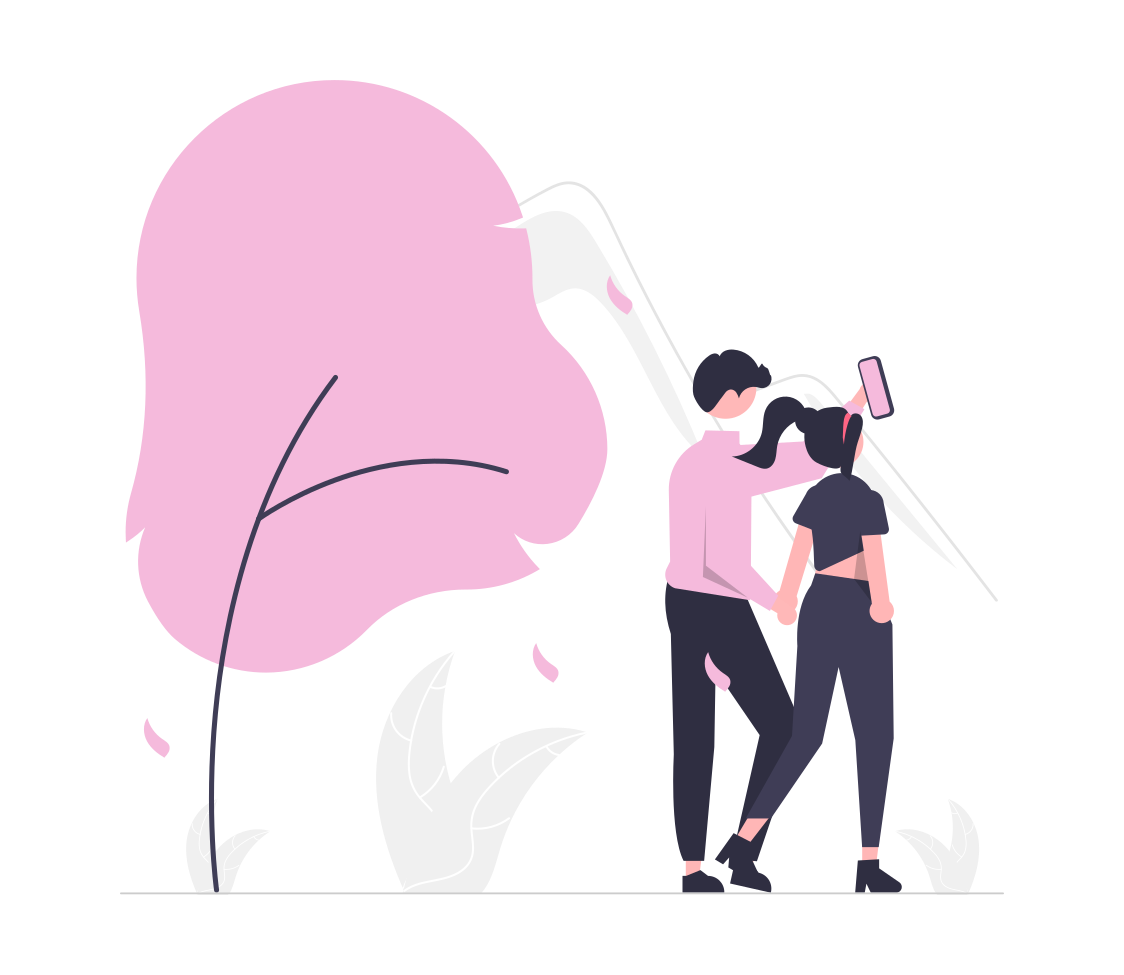こんにちは、femifeのカラスです。

- うちの子は、家だとひょうきんなのに園では無口だと言われる
- 人見知りが強くて、家の人以外だと全然話をしない
こんな方へおすすめの内容です
- 人見知りは、自我が芽生え、自分・自分の世界にいる人(保護者や家族)と、自分以外とで線引きがされる正常な発達。
- 人見知りをしても、時間をかけると慣れる場合は問題はなく、むしろ人見知りをしない方が心配なこともある。
- 時間や環境を変えても家以外で話せない場合は、「場面緘黙(ばめんかんもく)」の可能性もあり、早期に安心できる環境を整えてあげることが重要。
なんで人見知りをするの?
人見知りは、自分の世界と他人の世界を持っていることが始まる理由です。
自我が芽生え、自分・自分の世界にいる人(保護者や家族)と、自分以外とで線引きがされます。
その時の「自分以外」がどの範囲になるかは、その子次第です。
性格や環境などにより違いがありますが成長していくと、園のおともだち・園の先生・祖父母から、初めて会うお友達など、自分以外の存在を認識していきます。
もちろん人見知りをしても、徐々に仲良くなるのが標準な流れなので、程度の問題とも言えます。詳しくは以下で説明します。

人見知りをすることは悪いの?
もちろん、人見知りをすること自体は全く悪いことではありません。
むしろ誰にも人見知りしない方が、自分と他人の境界線がないことになるため、適切な発達とは言えません。
大人でも、初対面なのに敬語を使わなかったり距離が近かったりすると、戸惑いますよね。
子どもにとっては、見たことがある人かどうかが基準の一つになります。
見たことがない人、苦手な見た目をしている人などに、より抵抗を示すのは大人と同じです。
つまり、人見知りをしても程度の問題のため、日常生活に支障があるかどうか・子ども本人が困っているかどうか、それによって対応が必要か考えると良いでしょう。

外だと全くお話し出来ない子
人見知りに似ていますが、家の中では楽しく過ごせているのに、違う場所に行くと全くお話し出来なくなる子がいます。
保護者など信頼できる人と一緒であれば話せるようになる場合や、園の先生など時間をかけて慣れられる場合は問題ありませんが、そうでない子は、気にしてみてあげてください。
何故かと言うと、その子が困っていることを伝えられる能力が(家では)あるのに、外ではその能力を発揮できないと言う状況は、その子にとって非常に困る状況だと言えます。
それを、程度によっては「場面緘黙(ばめんかんもく)」と言われることもあります。
場面緘黙(ばめんかんもく)
園など(時間をかけることでリラックス出来る環境になる状況なのに)では、1か月以上声を出して話すことができないことが続く状態を、「場面緘黙(ばめんかんもく)」と言います。
人見知りとの違いは、リラックスしていても話すことができないこと、数分数時間ではなく長期で状況が改善しないことがあります。
原因などはまだはっきりとはわかっていません。
時間をかければ自然と治るものでない場合が多いため、なるべく早期に、その子が安心して過ごせる環境を増やしてあげることが重要です。

- 人見知りは、自我が芽生え、自分・自分の世界にいる人(保護者や家族)と、自分以外とで線引きがされる正常な発達。
- 人見知りをしても、時間をかけると慣れる場合は問題はなく、むしろ人見知りをしない方が心配なこともある。
- 時間や環境を変えても家以外で話せない場合は、「場面緘黙(ばめんかんもく)」の可能性もあり、早期に安心できる環境を整えてあげることが重要。

場面緘黙は、その子自身も不安ですし周りの目を気にして二次的な問題に発展する可能性もあります。なるべく早く子どもの困り感に対応していけるといいと思います。ご精読ありがとうございました。